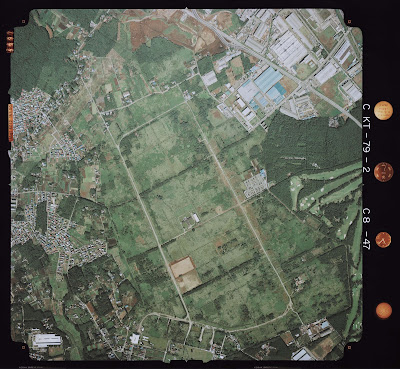先日、赤穂、姫路という播州の名城2つをブログに書いた。
日本百名城の一つ、明石城の写真も数枚あるので書いておく。
訪ねたのは姫路城にいった2015年3月27日の早朝。
神戸で開催された日本薬学会に来たのだが、神戸に宿が取れず、西明石から通った。
25日の夜に来て、26日の朝、車中から明石城を見てその近さに驚き、この日、早起きしたのである。
2015₋03₋27 6:53
ホームから見えるというのは備後の福山城を思わせる。
山陽道は海の近くを通り、明石城はそれを塞ぐような位置にある。
姫路城とともに西国大名の東進を抑える役目があった。
駅から来て濠を渡ると三の丸
その北の高地に西から本丸、二の丸、東の丸が連郭式に並ぶ。
7:01
三の丸から本丸上の乾櫓、巽櫓をのぞむ。
巽櫓は辰巳(南東)であっているが、乾櫓は戌亥だから北西、ここではない。
本来なら坤(未申)である。
明石城は西国の抑えとして幕府が援助して築城されたが、天守が建てられなかった。二つの櫓は天守の代用としてシンボル的な存在であり、南側に並べられた。櫓の名で多いのは巽と乾で、縁起も良いとされる。そのことから実際の方角とは関係なく命名されたのだろう。
平日朝だから観光客はいないが、城内を近道に突っ切る通勤の人が少しいる。坂を二の丸に上がり、空堀を渡って本丸に入った。
7:09
巽櫓ごしに朝日を浴びる明石大橋がくっきり見えた。
江戸時代初期は姫路池田家の領地であったが、1617年池田光政が鳥取に移った。すると信州松本藩8万石の2代目、信頼厚い譜代大名の小笠原忠真が明石10万石に国替えされ、明石川西岸の船上城に入った。すぐに幕府から築城を命じられ、現在地に着工、1620年正月には藩主が移り住んだ。城下町の町割りは、当時小笠原忠真の客分だった宮本武蔵が指導したとされる。
しかし1632年、小笠原忠真は豊前小倉15万石に移封され、この家は九州外様大名と対岸の毛利家の監視役として、幕末まで続く。
ちなみに小笠原氏というのは武田氏と同じく甲斐源氏の一流とされ、戦国時代は信濃の国の守護をつとめた。しかし武田信玄に敗れ、以後は武田氏に従属した。武田氏滅亡後、信濃は空白地帯となり上杉、織田、徳川の草刈り場となったが、地侍たちが旧主小笠原長時の息子貞慶を迎え、貞慶は家康についた。
秀吉政権となっても貞慶は嫡男秀政を家康に人質としてだし、信州松本平の所領を安堵された。しかし天正18年(1590)の小田原征伐で北条氏が滅亡、家康が関東に移封されると、秀政も家康に従って関東に移り、下総古河に3万石を与えられた。
(このあと松本に入ったのが家康の重臣でありながら秀吉に走った石川数正である。)
古河の小笠原秀政は関ヶ原の後、1601年、故郷に加増されて戻され、秀政は信濃飯田藩5万石を経て、松本藩8万石の藩主となった。しかし秀政と嫡男忠脩は1615年の大坂夏の陣で戦死し、あとは次男の忠真が継いだ。彼が1617年、松本から明石に入封した初代である。
本丸の縁に立つと絶景である。
7:10
南方に駅、電車、海、淡路島
しかし戸田松平氏は5年で美濃に移封、以後、明石藩は次々と様々な譜代大名が入る。しかし1682年、越前大野藩より松平直明が6万石にて入封した。
彼は結城秀康の孫にあたり、以後この家は明石松平家と称し、10代目が廃藩置県を迎えた。親藩大名であり、明石8代目の斉宣は11代将軍・家斉の二十五男で、この時2万石の加増を受け、8万石(10万石格)となった。
本丸の北側に行ってみた。
7:13
平山城だから本丸、二の丸などは南の三の丸より高く、本丸北側は崖になっている。
日本100名城にふさわしい石垣、保存状態である。
駅前にこれだけのものがあるとは、明石も大きな財産をもっている。
本丸の南側石垣の上でみた明石海峡大橋に行ってみたくなった。
明石から上り電車に乗って朝霧のつぎ、2つ目の舞子駅で降りるとすぐ。
7:45
明石海峡大橋
つい「明石大橋」と言いたくなるが、それは明石の西側、明石川にかかる国道2号線の橋である。また、ここは明石市ではなく神戸市垂水区になることからも「海峡」の文字は必要である。
一帯は県立舞子公園。
架橋工事と埋め立てでできた土地を、大橋の完成とともに公園にしたものだと思ったら違った。
ここは舞子浜といって、源氏物語ゆかりの須磨、明石や高砂などともに、播州海岸において古くから風光明媚とされる景勝地であった。(須磨は摂津だが)
播磨の舞子は江戸時代から白砂青松の美しい海岸として知られ、明治時代に入ると明治天皇や有栖川宮が訪れ、政財界人の別邸が近隣に建設されるようになった。1900年(明治33年)に全国的にも珍しい県立公園として「舞子公園」が開設された。
戦後、排ガスなどの影響か多くの松が枯れたが、関係者の努力で松林が復活しつつあった。しかし明石海峡大橋の工事で松の移植を余儀なくされ、橋の完成後は南の埋め立て地が公園となり松が300本植えられたそうだ。
さて、明石海峡大橋は、瀬戸大橋(1988開通)より新しく、
着工: 1988年(昭和63年)5月
供用: 1998年(平成10年)4月
主塔高: 298.3 m(海面上)
中央径間(支間): 1,991 m
(2022年3月まで世界最長のつり橋だった)
全長: 3,911 m
桁下65メートル、この下を2025年1月、飛鳥IIでくぐった。
7:46
淡路島
そういえば、1990年7月淡路島の病院で神経外科の医師たちのセミナーの講師に呼ばれ、そのときは神戸からフェリーだった。
2015年、この日は慌ただしく明石海峡大橋を後にして、学会会場の神戸ポートアイランド、神戸学院大学に向かった。そして午後になって学会会場を抜け出し、姫路城の見物に行ったのだから、濃い1日だった。
過去のブログ
20250430 姫路城、行かずに10年前の写真で書く
20250423 赤穂は江戸時代最先端だった名城を復元しつつある
20250201 クルーズ5 瀬戸内海と船内の食事
20111103 谷中墓地9 松平家はいくつあるか?十四松平から御連枝まで